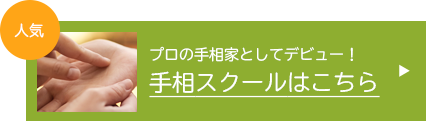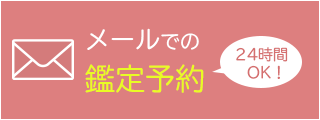2008/07/27 手相家まるちゃんも「蟹工船」若き日に読みました
最近、古典文学というべき小林多喜二の「蟹工船」が大増刷のベストセラー!ということを耳にして非常に複雑な思いを抱いています。昨年までは月に5000冊平均で売れていたそうですが今年はここ数ヶ月で何万部も!この本が読まれる背景には世情不安と雇用に関する不安と諦めがあると私は思っています。
小林多喜二は私の生まれた秋田県鹿角市のお隣町の現在の大館市に生をうけています。いわゆる地元の有名人でもあるわけですが、日本のプロレタリア文学の代表的な作家です。
この「蟹工船」は国際的にも非常に評価の高い作品で数多くの国で翻訳されています。
詳細はwikipediaより抜粋しますね。
あらすじ
カムチャツカの沖で蟹を獲りそれを缶詰にまで加工する蟹工船「博光丸」。
それは様々な出自の出稼ぎ労働者を安い賃金で酷使し、高価な蟹の缶詰を生産する海上の閉鎖空間であり、彼らは自分達の労働の結果、高価な製品を生み出しているにも関わらず、蟹工船の持ち主である大会社の資本家達に不当に搾取されていた。
情け知らずの監督者である浅川は労働者たちを人間扱いせず、彼らは懲罰という名の暴力や虐待、過労と病気(脚気)で倒れてゆく。
初めのうちは仕方がないとあきらめる者もあったが、やがて労働者らは、人間的な待遇を求めて指導者のもと団結してストライキに踏み切る。
しかし、経営者側にある浅川たちがこの事態を容認するはずもなく、帝国海軍が介入して指導者達は検挙される。
国民を守ってくれるものと信じていた軍が資本家の側についた事で目覚めた労働者たちは再び闘争に立ち上がった。
【再脚光】
作者の没後75年にあたる2008年の日本では、新潮文庫『蟹工船・党生活者』が古典としては異例の27000部を増刷、例年の5倍の勢いで売れ、5月2日付の読売新聞夕刊一面に載った[1]。若者、特に就職氷河期世代に人気である。
就職氷河期世代の多くは非正規雇用などの不安定労働者であり、ワーキングプアも少なくない。一流大学を出ても就職ができずに苦しんでいる者もおり、小林多喜二の捉えた世界観は今日の若者の現状と通じるものがあることを示している。
(ここまで)
実際、働いているものにとっては過去の蟹工船で働いた方たちと現代の閉塞感漂う労働環境は非常に似通っているものといえます。
私が就職した1995年当時は就職氷河期時代でしたね。団塊ジュニアと表される私たち1972年生まれは結構、苦難の道を歩んできたように思います、正直。しかも、年功序列型社会の崩壊をその目で見て、しかもそれを確かめてきた世代ですから!よく分かりますね。「蟹工船」が今の若者に圧倒的に支持される理由は。
私は高校時代にこの「蟹工船」を小林多喜二が生まれた大館で通学電車の中、読みふけりました。当時、世にいう文学少年だったんです。(その当時も手相には非常に興味を持っていましたが、手相のとりこになったのは大学時代の東京ですね)
今や、年功序列型社会はほぼ原形をとどめていません。私は富士通に見られるような成果主義の失敗の教訓は、日本の全ての企業に生かされるべきだと思っています。ひょっとしたら日本には成果主義は土壌的に似合わないのかもしれません。賃金が頭打ちになった時に生まれるのは、仕事のやる気の低下ですから。そのあたりは、やはり少しづつでも毎年お給料が上がった昔の日本が良かったのかもしれません。下の者が50歳代の方を見て「あの人、あまり仕事しないけど、そこそこ給料もらっているんだろう」みたいな変な安心感があったように昔はあったと思うんですね。
今は、頑張っただけそれが会社に評価してもらえているか不明な部分もあり、仕事に対する意欲の低下があると今年の「労働白書」に出ていましたが、それはまさにその通りだと思います。
そこで世の中に絶望して、そこでなぜか自分ではなくて全く関係のない他人をあやめてしまうこの昨今の事件には、目を覆いたくなるものばかりです。
この国は、いったいどこに舵を向けて動いていくのか。
個人レベルでいえば、どんな意欲の湧かない環境であっても、何かひとつでもやる気を保つ対象物があればそれは非常に幸せなことと思います。結局は世の中の最初も最後も「自分」をいかに生き生きさせていくことができるか勝負なんだと思います。
幸い、私は過去においては職場にも恵まれて、仲間にも恵まれて、家族にも恵まれて生きてきましたが、人に言えないような苦労も葛藤もしてきました。その分、磨かれたんだと思いますが、今、たとえば絶望の日々を送っている方がいたら、鑑定うんぬんではなく、気軽に、メールや「無料手相カウンセリング」から世の中の不満や愚痴でもいいので、私は受け止めることができると思っていますので書いてみて下さい。
小林多喜二は最後は国によって葬り去られてしまいましたが、彼の思想や本当に言いたかったことは私も「蟹工船」を通じて学びました。彼は、死しても尚、その輝きを失っていないのです。